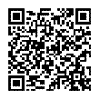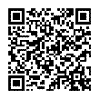詐欺なのにクレジットカードが止まらない!
詐欺で騙されたのに、その支払いをクレジットカード等で行っていた場合、クレジットカード等の支払いが自動的に止まるという事はありません。なぜ止まらないの?
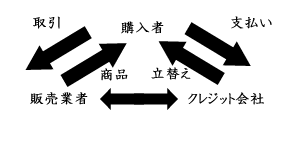
例えば、商品をクレジットカードで買った場合、商品やサービスについては業者と、クレジットカードなどについては、クレジット会社と契約しています。つまり契約の相手が異なるので、止まることはないのです。では、どのような条件で何をすれば支払いを止めることができるのでしょう。
支払い停止の抗弁書がある!?
下記が支払停止の抗弁書に使える条件です。よく読んで理解しましょう。
売買契約が成立していない場合
商品が届いていない、破損、故障など
詐欺・強迫などで取消ができる場合
錯誤や公序良俗に違反する場合
未成年等で契約の取消ができる場合
クーリングオフで契約を解除できる場合
特定の役務提供の場合で中途解約した場合
法律「割賦販売法」
(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
割賦販売法 (法令ナビへ)
解説
2ヶ月以上の期間で3回以上の分割払いのカード決済(割賦購入斡旋)やローン提携販売であることで、割賦販売法で定める指定商品・指定役務・指定権利であることが前提で、上記で示したような販売業者に対しての抗弁事由があり、支払い総額が4万円以上(リボは3万8千円以上)で、事業者の契約が商行為でない場合に、支払停止の抗弁権が使えるという事になります。
例えば、エステティックサロンや英会話教室でその料金をクレジットで支払っていた場合で、突然サロンや教室が閉鎖された場合、クレジットカードで毎月引き落としが合ったり、提携ローンで年間契約等をしている場合は、その役務の料金が4万円以上で2ヶ月以上3回以上の約定等であるといった場合は、支払い停止の抗弁書でその後の支払いを免除できると考えられます。
支払停止の抗弁書はどうやって書くの?
支払い停止の抗弁書については、内容証明郵便(配達証明書付)でクレジット会社等に送るのが通例のようですが、契約のクレジット会社に「支払い停止の抗弁書を送ってください」と申告すれば、ほとんどのクレジット会社やローン会社が送ってくれます。
また、最寄の役所にある消費者センターで相談をすれば、書き方の指導をしてくれるはずです。
書式は、社団法人クレジット協会のHPからもPDFで入手する事が可能です。
支払停止の抗弁書面について(PDF、社団法人クレジット協会より)
<書面構成>
どのクレジット会社に送るか?
どのようなクレジットカードで契約者は誰か?
そのクレジットカードでどのような契約をしたか?
支払い停止の抗弁をするに当たっての理由は何か?
業者とどのような交渉をしたか?
きちんと詳細に日時やカード番号、相手の住所等を書かなければなりませんので、契約時の書類に基づいて書く必要があります。契約書面等は予め大切に保管しておく必要があります。
<注意点>
必ずしも内容証明郵便である必要はないので、この点はさほどこだわる必要はありません。なぜなら、内容証明郵便は、このような内容の物を贈ったという事実のみの証明であって、それ以外の法的な強制力を課すものではないからです。
ただし、この「支払停止の抗弁権」については送達の日時や送ったという証明が非常に重要なので、配達証明をつけて送ることが最も重要です。
例えば、社団法人クレジット協会が提供しているひな型は内容証明郵便では送れませんので、見本を見て内容をできる限り詳細に書き、送付内容と同じ物を手許に残しておくようにコピーしておけば、良いでしょう。
(使える事例1)詐欺業者の通信販売
詐欺業者がインターネット通信販売で、クレジット決済を利用していた場合で、条件に見合う場合、当然、商品が送られてこなかったり、頼んだものとは全く異なる内容の物が送られてきます。
悪質会社も同様で、解約に応じない等の様々な悪質な対応をします。
こうした場合、クーリングオフが使える場合は、クーリングオフ、使えない場合は、民法96条の1詐欺取消や消費者契約法の不実告知等を理由に、取消権を業者に対して行使します。
この場合は、内容証明郵便で配達証明付の通知書で十分でしょう。
それとほぼ同時に、支払い停止の抗弁書を作り、その取引の際に利用したクレジット会やローン会社に送ります。
これで、クレジットが停止されると、詐欺業者や悪徳業者には、支払がいきません。ただし、それまで払っていたお金はこの抗弁書では取り戻すことは出来ないので、返還を求める場合は、別の手続が必要だと考えられます。
※ クーリングオフや無効との判断の場合は、支払済みの金銭が返還される場合があります。
詐欺業者にブラックリストに載ると言われた!
詐欺業者や悪徳業者はあの手この手で、この支払い停止の抗弁権を被害者が使わないように画策を張り巡らせます。
多くの場合では、支払い停止の抗弁書を送ると、クレジット会社が損をするから、ブラックリストに載る等と言って、断念させようとします。
ところが、この制度は消費者保護の観点から作られていて、簡単に言えば、悪徳業者からの被害や詐欺の被害から救済するためのものです。
その主旨で、これを利用した人がブラックリストに載るのでは、本末転倒な制度になってしまいます。ですから、この支払い停止の抗弁権を行使しても、ブラックリストに載ることはありません。
心配な方は、契約のクレジット会社やローン会社に問い合わせをしてみることをお勧めします。
注意
支払い停止の抗弁については、ただ気に入らないからというような理由で行使できるものではありません。またこれを利用したからといって、絶対に支払が止まるというものでもありません。
ですから、支払い停止の抗弁書を検討する際は、諸条件をきちんと確認して行う必要があります。
また、理由や条件に不備がある場合は、クレジット会社から裁判を提訴される場合があります。
タイムラグの節約
支払い停止の抗弁書を送る等、適切な手続きを行っていても、審査やクレジット会社などの調査で支払いのタイミングに誤差が出る場合があります。
こうしたタイムラグによる欠損が出ることを極力避けようとする場合は、引き落とされる自分の銀行口座で契約されている口座振替契約の解除や、当該口座の残高を0円にしておく、解約してしまう等の方法で対処ができます。
方程式ではない解決
詐欺や悪質商法全般にいえることですが、何かをすれば必ず解決するといった方程式は原則的にありません。
また、同じカテゴリーに属するような詐欺であっても、全ての手口が同じわけではなく、被害形態も同様の詐欺であっても被害者によって異なることは、多く確認されています。
そして、このそれぞれの手口を全て同じ調査方法や手続で終結できることは、ほとんどありません。
ですから、商品を買うような感覚でプロに相談すると、必ず詳しく資料等を見ないと回答のしようがないと言われてしまいます。逆に二次被害を巻き起こすような業者に相談すると、ドンブリ勘定で150万とか300万とか法外な金額を提示されます。
ですから、色々なプロに相談する場合は、解決へのどんなアプローチが自分にとっていいのか検討しながら、自分の被害をきちんと説明することをお勧めします。